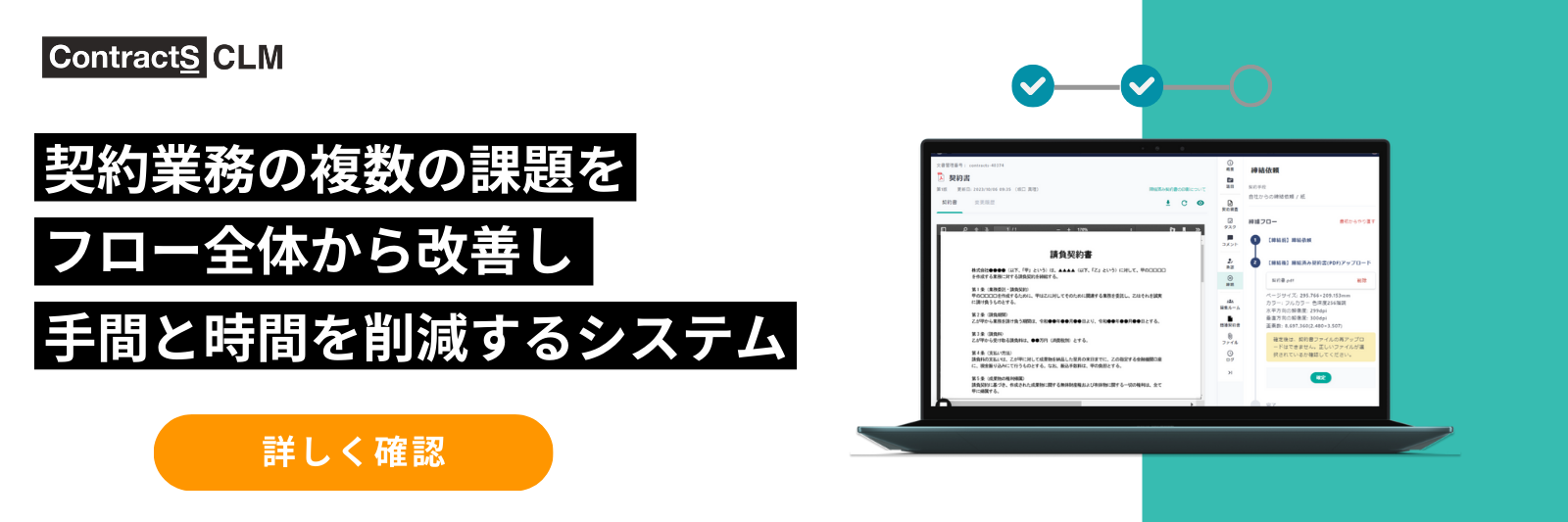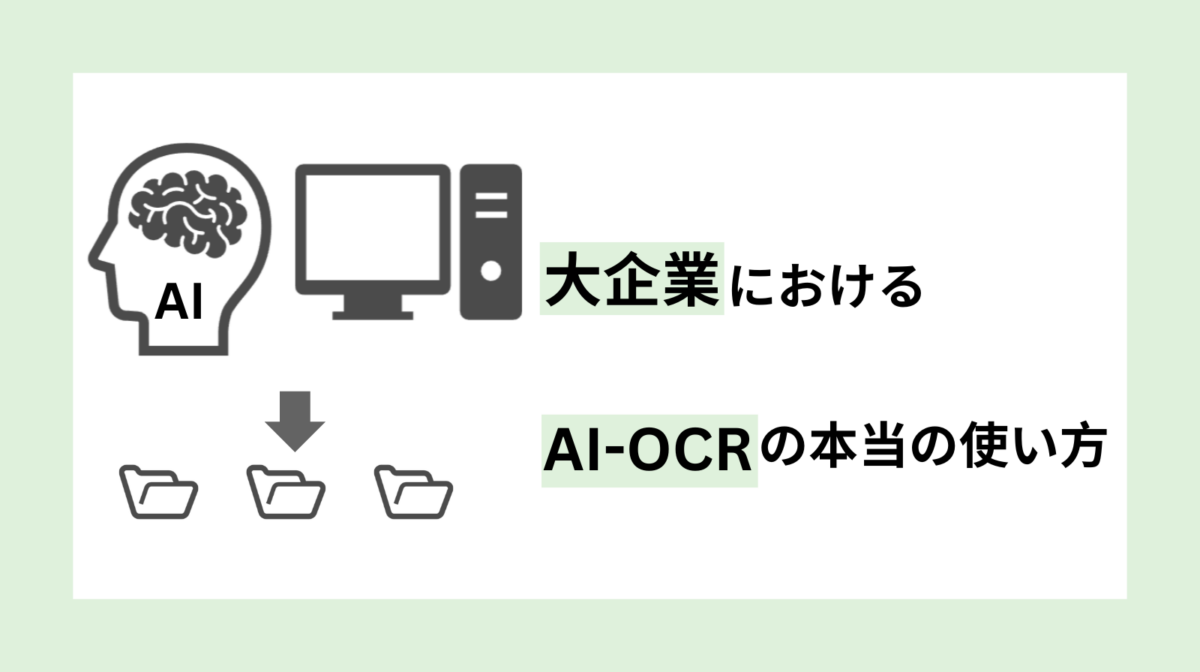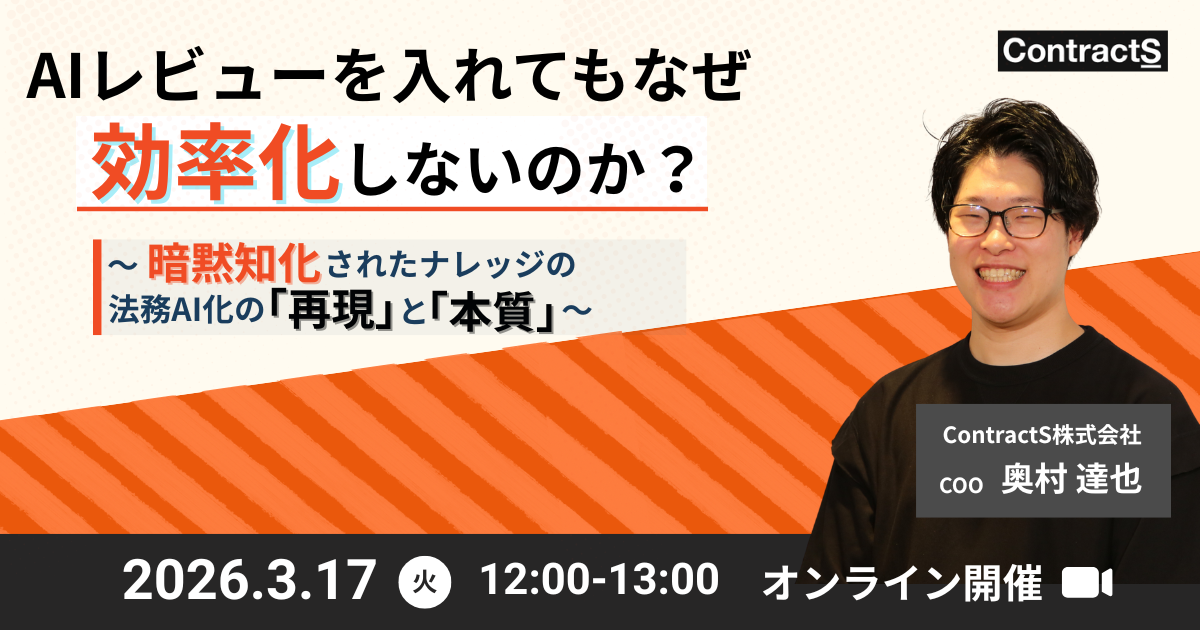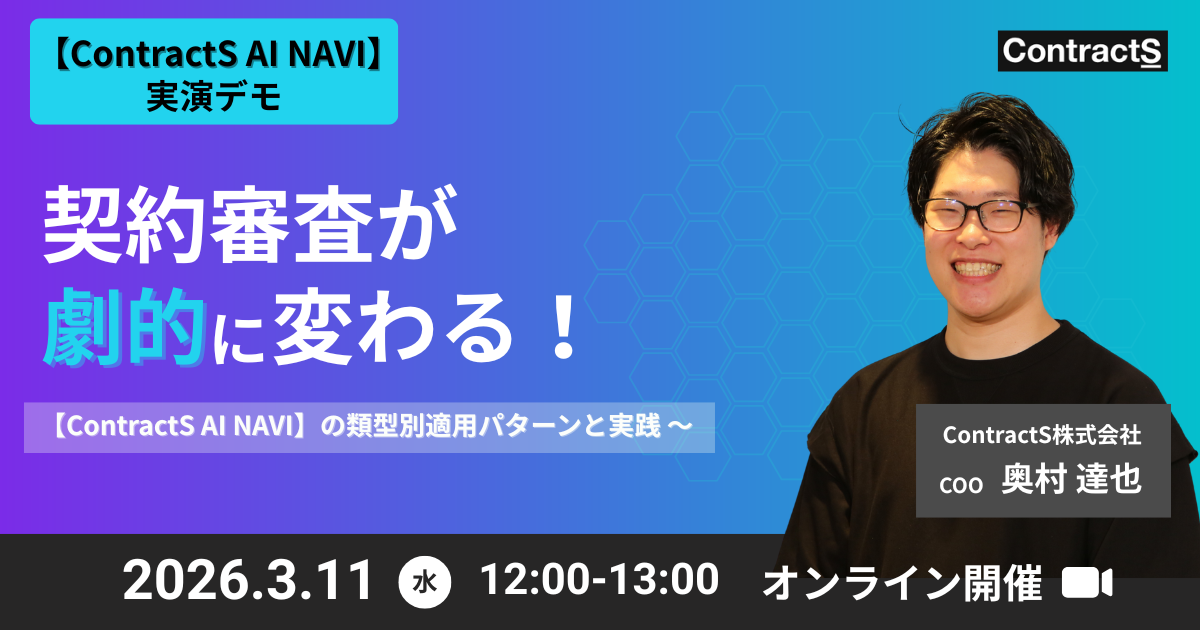ノウハウ 契約管理だけのツール導入で終わらせない ― 契約業務全体を見直す視点とは?
投稿日:2025年10月2日
契約管理だけのツール導入で終わらせない ― 契約業務全体を見直す視点とは?

契約DXの波に乗り、多くの企業が「まずは契約管理ツールから」と導入を進めています。締結済み契約書をデータで保管し、検索や更新期限を管理できるようになった企業も少なくありません。
しかし、実際に運用してみると「期待したほど効率化できていない」「情報が分断されて逆に煩雑になった」という声が多く聞かれます。
そこで今回は、「契約管理にツールを導入しただけではなぜ効率化できないのか?」課題を整理し、契約業務全体をどう見直すべきかについて解説します。
契約管理ツール導入後に浮き彫りになる課題
1. 複数システムによる負担増
電子契約、レビュー支援、契約管理――用途ごとに別々のツールを使うと、アカウント管理やシステム間の行き来に大きな負担が生まれます。法務部門だけでなく情シスにも、ログイン管理やセキュリティ対応といった新しい業務が増えてしまうのです。
2. 契約ステータスが不明瞭
契約管理ツールには「締結済み」と表示されていても、実際には社内承認が未完了というケースが少なくありません。部分的なシステム導入では、「いま契約がどの状態にあるのか」が全社的に把握しづらくなるという矛盾が生まれます。
3. コストが積み上がる
契約管理だけでなく、レビューや電子契約のツールを個別導入していくと、月額費用や初期費用が積み上がります。結果として「思った以上にコストがかかるのに、業務は思うように効率化されない」という本末転倒な状況に陥りがちです。
4. 情報探索に時間がかかる
契約書そのものは管理できても、交渉履歴や承認経緯がメールやチャットに散在しているケースは多いでしょう。必要なときに「なぜその修正をしたのか」「過去の類似契約ではどうだったか」といった情報を探すだけで膨大な時間がかかります。
5. コミュニケーションが分断される
事業部はメール、法務はチャット、経営層は会議…と、ツールごとにやり取りが分断されると、修正理由や判断根拠が履歴として残らず、追加の打ち合わせが必要になります。これではスピード感を持った事業推進が難しくなります。
本当に必要なのは「契約ライフサイクル全体」を見る視点
これらの課題は「契約管理」という最後の工程だけをツール化しても解決しません。
契約は、依頼・相談 → 契約書作成 → 審査・承認 → 締結 → 管理・更新 というライフサイクルで成り立っており、その一部だけを切り取って効率化しても、全体としては依然として分断されたままです。
そこで注目されているのが**CLM(Contract Lifecycle Management)**という考え方です。CLMは、契約ライフサイクルの各フェーズを一貫して管理し、契約データを全社で活用できる仕組みを提供します。
例えば:
・契約書検索時に、審査履歴や交渉経緯も含めて把握できる
・契約更新や終了期限が明確になり、次のアクションが遅れない
・アクセス権限の設計により、必要な人がすぐに必要な情報にたどり着ける
・属人的な台帳入力やフォルダ検索から解放され、ナレッジが組織に蓄積される
これにより、契約は単なる「リスク管理のための保管」ではなく、事業を推進するためのデータ資産へと変わります。
まとめ ― 部分最適から全体最適へ
契約管理ツールの導入は大きな一歩ですが、それだけでは契約業務全体の効率化は実現できません。
複数システムの乱立、情報の分断、コスト増といった課題を解消するには、契約ライフサイクル全体を見渡し、統合的にマネジメントする視点が不可欠です。
その実現を可能にするのがCLMです。
「契約締結後の管理」だけに留まらず、契約業務を俯瞰して改善することで、法務部門だけでなく事業全体のスピードと精度を高めることができます。
契約業務の効率化に本気で取り組むなら、いまこそ「部分最適」から「全体最適」へと舵を切るべき時です。
もし、詳しく知りたいなどあれば下記より資料ダウンロードください。